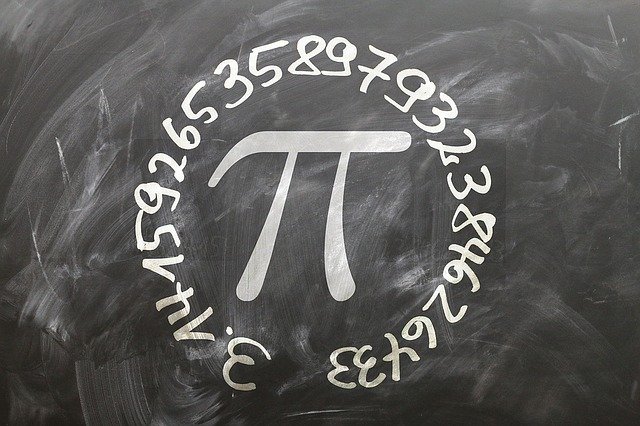分散型自律組織( DAO )とは? 特徴・問題点ほか
近年、仮想通貨等の新たな通貨が台頭してきました。
NFTやメタバースなどの登場によって注目を集めているのが、WEB3.0です。
これまで当たり前に存在したWEB2.0 とは大きく異なり、分散型インターネットという次世代の方式だと考えられています。
その中で重要となっているワードが、分散型自立組織です。
そこで今回は、分散型自律組織について誰でも分かるように解説していきましょう。
目次
分散型自律組織(DAO)とは?

DAO(Decentralized Autonomous Organization)は、日本語に訳すと「分散型自律組織」となります。
ブロックチェーンに基づく組織や企業の形態の一つで、特定の中央管理者を持たず世界中の人々が協力して管理・運営される、コンピュータやネットワーク、ノードによって自動化と分散化がされた組織のことです。
もちろん、中央管理者を持たないため政府などにも支配されません。
そのため、ブロックチェーン上のスマートコントラクトにコード化されており意思決定には組織全員が参加でき、提案と投票が用いられ、グループの承認なしでは何も決まらないことになっています。
また、今後暗号資産業界のプロジェクトの多くはDAOによって管理されると言われています。
まだBybitの取引所を開設していない方はまずは仮想通貨取引所の登録手続きをおこないましょう
詳細はBybitの取引所開設をご覧ください
分散型自律組織(DAO)の特徴
分散型自律組織(DAO)には、いくつかの特徴があります。
・オープンソースで透明性が高い
・NFTやメタバースと関連付けられている
・所有権が分配されている
そこでここからは、分散型自律組織の特徴について詳しく見ていきましょう。
管理者がいない

中央集権的な組織に支配されず、リーダーや社長のような人がいません。
元々ある独自のルールに従い、ブロックチェーン上で実行されるため誰かがその仕組みを勝手に変えることもできません。
もし、仕組みなどを変える際は投票で決めることになります。
そのため、不正がなく安心して参加できます。
オープンソースで透明性が高い・誰でも参加可能

管理者がいないだけでなく、全てのDAOによる情報は公開される完全自立型のため透明性が高いと言えます。
ルールや組織、オープンソースのブロックチェーン上に構築されているため誰でも情報を見ることができ、財務情報も監査することができます。
そのため、インターネットにアクセスさえできれば誰でも参加でき、DAOトークン保有、購入することができ、意思決定権を持つことができ参加できます。
また、事業の資金集めや寄付をするためにDAOを設立することもでき、誰でもDAOを作るのが可能で、外部の人材採用・物品発注も理論的に可能です。
もちろん、誰でも参加などができますが、サービスを利用されたり、資金を提供してもらうのは運営者次第になります。
NFTやメタバースと関連付けられている

例えば「Decentraland」というDAOでは、仮想世界で「LAND」と呼ばれる土地を購入でき、NFTをユーザー同士で取引することができます。
また、PleasrDAOではNFTの収集をするDAOであり、投資家同士で資金を出し合ってNFTを購入しています。
ちなみに、NFTを担保にして資金の借り入れをしたDAOはPleasrDAOが初めてで、DeFiプロトコルである「Cream Finance」から仮想通貨を借りたことで知名度を上げました。
所有権が分配されている
DAOは、中央集権が用意されていません。
そのため、組織自体の所有権を分配するという考え方が採用されています。
この所有権を示しているのが、ガバナンストークンです。
DAOでは、開発者や提携パートナーに主に分配されていますが、DAOへの貢献具合によってユーザーにも付与されます。
そのため、創業者や投資家に集中してしまうというリスクを避けることができるのです。
所有権を分配することによって、個人がDAOに対して価値を生み出すことができ、それに対する報酬を受け取ることができるようになっています。
DAO(分散型自律組織)が注目されている理由
DAOはまだ登場してまもないサービスですが、それでも世界的に大きな注目を集めています。
・WEB3.0の考え方が浸透してきている
・人気が高まっているNFTやメタバースとの関連がある
・誰でも運営することができる
では、どうしてここまでDAOは人気があるのでしょうか?
DeFiを発展させたものがDAOだから
DAOと同じようなシステムと言われているのが、DeFiです。
ブロックチェーン上で構築されている金融サービスのことを指している言葉。
金融機関が仲介しなくても個人同士でやりとりを行うことができるので、時間と手数料を抑えた状態での取引が可能。
▼DeFiについて詳しく知りたい方はコチラ
DeFiは2021年頃から注目を集めて、大きな話題となりました。
このDeFiが活用されている組織形態のことが「DAO」ということになります。
つまり、DAOはDeFiの発展形ということができるので、これからDeFi市場が人気となればDAOの認知度が高まると予想されています。
現在は徐々にDeFiが当たり前となってきているので、DAOが認知されるのも近いといえるでしょう。
WEB3.0の考え方が浸透してきている
DAOへの注目が高くなった原因の1つに、Web3.0の認知が高まったことが挙げられます。
これまで当たり前に使ってきたインターネットはWeb2.0と呼ばれており、中央集権型となっていた。
これまでのシステムの問題点となっていたセキュリティ面やプライバシーの問題を解決することができるので注目されている。
▼Web3.0の考え方を詳しく知りたい方はコチラ
WEB3.0は、これまでのインターネットの問題となる点を解決することができるシステムとなっているため、注目されています。
これを実際に組織運営の形としているのがDAOなので、共に発展していくのではないかと言われています。
人気が高まっているNFTやメタバースとの関連がある
DAOは、現在徐々に浸透してきているNFTやメタバースともさまざまな関連性があります。
NFTやメタバースは誰でも参入できる仕組みとなっていますし、多数の大手企業が参入してきていることから、注目度が高くなっています。
NFTとメタバースと一緒に、DAOの存在感が大きくなることは予想できるでしょう。
▼メタバースについて知りたい方はコチラ
誰でも運営することができる
DAOは、参入障壁がかなり低くなっています。
それは、インターネットを使える環境であればだれでも運営することができるからです。
これまでのシステムではさまざまな手順を踏んで取り組む必要がありましたが、それがない分より一気に発展していくのではないかと期待されています。
分散型自律組織( DAO )の問題点
分散型自律組織(DAO)は、魅力的な面もたくさんなりますが、まだ問題となっている部分も存在します。
・ハッキングのリスクがある
・法整備が未発達となっている
・一度決めたルールを変えるのが大変
そこでここからは、DAOを利用する上での注意点について見ていきましょう。
問題点の修正に時間がかかる

株式会社のような会社形態ではないため、管理者がいないことで参加者同士の合意により方向性やシステムの修正などが行われます。
しかし、何か決める際に必ず参加者の合意がなければならず、社長などが独断で決めるなどということができないため時間がかかってしまいます。
すぐ解決しなければいけないトラブルの際も合意を得るのに遅ければ死活問題になってしまいます。
また、参加者が多ければ多いほど合意に時間がかかってしまいます。
ハッキングリスク

先ほどの問題点の修正に時間がかかることで、その間にハッキングされて、仮想通貨が盗まれる可能性があるというデメリットがあります。
実際に2016年6月THE DAOはプログラムの欠陥からハッキングにて約360万ETH(約52億円)を盗まれる「The DAO事件」が発生しました。
この場合は参加者の合意により、ブロックチェーンをハッカーに盗まれる前の状態に戻ることで盗まれた資産を取り戻していますが、これを機に意見が保有者の中で割れ、イーサリアムクラシックが誕生しました。
法整備が未発達

日本だけでなく世界中でDAOに関する法律がまだ少ないです。
これから世界的な法律というよりも各国で法律が決められることもあるでしょう。
また、法整備が未発達なだけあって2017年にブームになったICOのように多額の資金を集めてそのまま持ち逃げしてしまう人もおり、大手取引所のハッキング事件もありました。(ハッキングされた分は保証されました。)
しかし、日本ではハッキングの被害を保証してくれるかもしれませんが、海外の取引所では保証してくれるかわかりません。
また、仮想通貨自体がサービスを終了したりなどしても誰も保証してくれません。
まだ日本の方が安心して取引ができるかもしれませんが基本的に自己責任となります。
一度決めたルールを変えるのが大変
DAOはまだ登場したばかりのサービスで、これから多くの問題点が出てくることが予想されます。
その場合、より使いやすいサービスにするために、既存のルールを変更していくことが必要となります。
しかし、DAOはブロックチェーンで管理されています。
ブロックチェーンは改ざん・修正をすることができない仕様となっているので、一度決めたルールを変更するのが非常に難しいと言われています。
このことから、組織としての柔軟性は少なく、臨機応変に方向転換するのは難しいと考えられるでしょう。
まだGato.ioの取引所を開設していない方はまずは仮想通貨取引所の登録手続きをおこないましょう
詳細はGato.ioの取引所開設をご覧ください
DAOの3つの種類
DAOは大きく分けて3つに分類されます。
・Bureaucratic DAO
・CEO DAO
それぞれシステムが違うので、理解しておきましょう。
Autonomous DAO
Autonomous DAOとは、自律的なDAOのことです。
完全に分散型のシステムとなっており、管理者がいなくてもスマートコントラクト上で自走することが可能となっています。
世間一般で言われている主なDAOは、このシステムであることが多いです。
Bureaucratic DAO
Bureaucratic DAOとは、官僚主義のDAOのこととなります。
複数の方が意思決定を行うというシステムです。
会社のように、社長や常務などの複数の方がいて、意思決定を行っているというとイメージしやすいでしょう。
本来の分散型のシステムとは少しかけ離れてしまいますが、従来のシステムに近い分導入されやすいというメリットもあります。
CEO DAO
CEO DAOとは、最高責任者が存在するDAOのことです。
1人が最終的な決定を下すシステムとなっています。
自律的な仕組みであるAutonomous DAOの方がメンバーの権利を守ることができると考えられていますが、意志決定を全員で行うというシステムがなかなか浸透しないことを考えると、このシステムを導入するところもあるかもしれません。
代表的なDAOのさまざまな導入事例
すでにDAOの仕組みはすでに多くのプロジェクトで利用されています。
・Augur
・和組DAO
・BitDAO(BIT)
・Uniswap (UNI)
そこでここからは、DAOの代表的な種類について詳しく見ていきましょう。
MakerDAO

MakerDAOとは、2014年に登場しており、DAOの中でも最も歴史があると言われているプロジェクトです。
MakerDAOの中のステーブルコインであるDAIは、ドルと連動しているので、自国の通貨の信頼性が低い国の場合、間接的にドルを購入する手段として使われる可能性が高いと期待されています。
ティッカーシンボル:MKR
価格:¥88,038(2023年3月27日現在)
時価総額:¥79,464,669,533(2023年3月27日現在)
発行上限:1,000,000MKR
公式サイト:https://makerdao.com/ja/
イーサリアムのブロックチェーンを活用し、ステーブルコインであるDAIを発行できます。
MakerDAOでは誰でもドルのステーブルコインを発行することが可能、DAO内での意思決定に関わることができます。
Augur

Augerという言葉は占い師、通貨のREPはReputation(評判)という意味から名づけられています。
つまり、仲介者のいない未来予想市場で群集の知恵という特性を生かすに開発されたプラットフォームのことを指します。
誰でも自由に予測ができることであればネットワーク上に乗せることができ、予測が正しければビットコインやイーサリアムなどで報酬をもらうことができます。
また、予測の結果を報告することによって、REPという通貨をもらうことが可能となっています。
ティッカーシンボル:REP
価格:¥1,133(2023年3月27日現在)
時価総額:¥8,905,719,152(2023年3月27日現在)
発行上限:11,000,000REP
公式サイト:https://www.augur-japan.com
分散型の予測市場プラットフォームで、参加すると「ビットコインは年内に1000万円を超えるかどうか」「次の米国大統領選ではどちらが勝利するか」などのさまざまな予測に対して投票で参加できます。
予測が当たればトークンを受け取れます。
和組DAO

日本でも注目されており、Web3について話し合うこと、Web3に理解のある日本人を増やすことを目的とし、実際にNFTを購入したり、DAOの意思決定に携わったりできる人を増やしていくのを想定したオープンコミュニティです。
DAOやDeFi・NFT・ブロックチェーン・メタバースなどに関心のある初心者や起業家などが参加しており、Discordのメンバーは2022年2月時点で3,700人を超えています。
BitDAO(BIT)

BitDAOとは、シンガポール発の大手取引所である「Bybit」が開発しているプロジェクトです。
BitDAOの目的は、将来有望なDeFiサービスを支援することです。
DeFi分野は近年大幅に発展し、多くのサービスが登場してきています。
しかし、その中にも優劣があるので、特に成長が見込めるプロジェクトへ資金やノウハウを提供することによって、市場全体がより活発になるように働きかけています。
ティッカーシンボル:BIT
価格:¥68.61(2023年3月27日現在)
時価総額:¥98,256,820,507(2023年3月27日現在)
発行上限:10,000,000,000 BIT
公式サイト:https://www.bitdao.io/
BitDAOのトークンであるBITは、BybitやFTX・Gate.ioで取り扱いしています。
目的は今後成長していくDeFiを発見し、出資・流動性の供給といった支援をすることです。
Uniswap (UNI)

Uniswapは、中央管理者が存在しない分散型取引所となっています。
仮想通貨自体は分散型となっていますが、これまでの取引所は中央集権となっており、その点が問題視されていました。
そこで登場したのが、DEXであるUniswapです。
Uniswapは注文スピードが速く、より手数料を抑えて売買することができるので、近年人気が高まってきています。
その上、仮想通貨の上場審査がないので、どのような通貨でも扱うことができるという点も魅力の1つと言えるでしょう。
ティッカーシンボル:UNI
価格:¥757(2023年3月27日現在)
時価総額:¥571,034,420,972(2023年3月27日現在)
発行上限: 1,000,000,000UNI
公式サイト:https://uniswap.org/blog/uni
分散型取引所(DEX)を提供しており、トークンはUNIです。
流通制マイニングという、特定の仮想通貨を預けてトークンを受け取ることであり、「UNI」を受け取れるというサービスがあります。
DAOを購入できる取引所

DAO関連銘柄を日本国内の取引所では取引することができません。
そのため、海外の取引所を利用する必要があり、DAOが購入できる仮想通貨に変換してから購入する必要があります。
海外取引所といっても、種類がさまざまあり、迷ってしまう方もいるでしょう。
そのような方には、BybitとUniswapがおすすめです。
どちらもDAOのサービスを扱っているので、手軽に利用しやすいでしょう。
日本人からの人気も高いので、安心して使うことができます。
DAOに関連している代表的な銘柄
DAOは近年、多くの注目を集めている分野です。
このように注目度が高まっている時には、それに関連する銘柄の価格が大きく伸びることがあります。
そこでここからは、DAOに関連している代表的な銘柄についてご紹介していきます。
・メイカー(MKR)
・Decentraland(MANA)
・BitDAO(BIT)
・Uniswap(UNI)
・Compound(COMP)
それぞれ特徴があり、どれも今後価格が高騰すると期待されているものなので、ぜひチェックしてみてくださいね。
メイカー(MKR)
メイカーとは、DeFiプラットフォームを手掛けているMakerDAOのガバナンストークンのことを指します。
他の通貨とは違い、決済手段として作られてはいるわけではなく、ガバナンストークンの役割のみとなっています。
しかし、MakerDAO自体が注目されているため、時価総額は高くなっています。
そのため、今後も期待が高まる通貨と言えるでしょう。
メイカー(MKR)は国内取引所であるGMOコインやBitbankでも取引を行うことができます。
保有していることによって、MakerDAOへの投票権も得られるので、メリットは大きいでしょう。
Decentraland(MANA)
Decentraland(ディセントラランド)とは、オンライン上で楽しむことができるメタバース空間です。
Decentralandの中では、MANAという仮想通貨が使われます。
MANAはDecentralandのガバナンストークンとなっていて、DAOによる運営を進められています。
すでにDecentraland上で行われたファッションショーには、世界的に代表的ブランドが扱われており、今後もこれ以上に注目が集まると期待されています。
国内の取引所でいうと、Bitbankで購入することが可能です。
BitDAO(BIT)
BitDAO(BIT)とは、海外取引所であるBybitに関連しているDAOのことを指します。
現在多数登場してきている「Defi」や「ⅾApps」などの分散型プラットフォームの開発を行うプロジェクトを支援することが目的となっています。
具体的には、Bybitの取引手数料の一部がBitDAOに流されており、この資金は将来有望なブロックチェーン技術やDefiプロジェクトへ投資されているということです。
BitDAOではBITがガバナンストークンとして流通しています。
BitDAOの背景には世界的に人気の高いBybitがあることによって、信頼性が高くて今後も期待されるといsて、BITの価値も大きく高まってきています。
Uniswap(UNI)
Uniswap(UNI)とは、分散型取引所であるDEXを提供しているDAOです。
分散型取引所とは、ブロックチェーンによって構築された仮想通貨取引所のことを指します。
元々仮想通貨の取引は、企業によって管理されている取引所によって実施されていました。
しかし、この仕組みでは通貨自体が非中央集権化されていても、本来得られる効果を手にすることができません。
それを解消するために登場したのが、分散型取引所(DEX)です。
DEXでは取引手数料を抑えることができる上に、取引所自体がハッキングに遭うリスクを減らすことができるので、安心して取引ができるようになると考えられています。
そんなUniswapで使われているトークンは、UNIです。
Uniswapで利用できる流動性マイニングを行うことによって、報酬としてUNIをもらうことが可能となっています。
現在、国内でUNIに対応している取引所はありませんが、海外取引所の場合はBinanceやGate.ioでは取引をすることができます。
Compound(COMP)
Compound(COMP)とは、イーサリアム上に構築されたDAOのことです。
Compoundは、仮想通貨の貸し借りを行うことができるレンディングプラットフォームとして使うことができます。
レンディングサービスとは、自分が保有している仮想通貨を貸し出すことによって、一定の手数料がもらえるという仕組みです。
銀行よりも利率が高いため、自分が保有している資産を仮想通貨に変換する方も多いです。
Compoundは他のサービスと比べると、利率が高い点が魅力となっています。
同じレンディングサービスを利用するのであれば、できるだけ利率が高い方がお得でしょう。
その上、レンディングサービスを使うことで、独自のトークンであるCOMPをもらえるのも特徴です。
現在は、COMPを扱っている業者は海外のみで、BinanceやCoinbase Exchangeで取引ができるようになっています。
いきなり海外取引所を使うのは難しいので、分からない方はまずは国内の取引所で扱われている通貨から始めましょう。