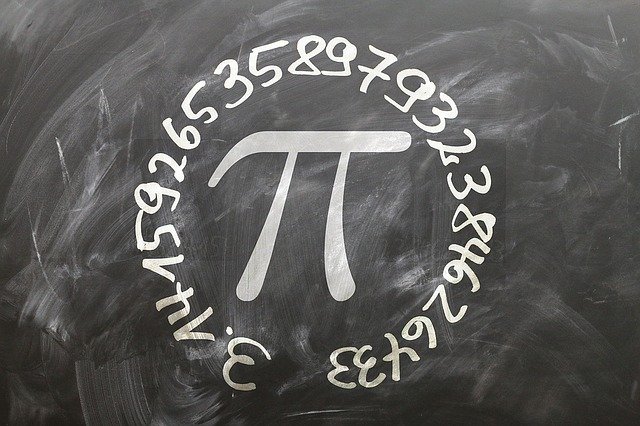【仮想通貨】レイヤー1 とレイヤー2の仕組みを解説!
レイヤー1、レイヤー2ということばを聴いたことはありますか?
仮想通貨について知っていても、パッと説明することはできない難しい内容だと思うかもしれません。
しかし、物事を一つ一つ理解していけば難しい内容ではなく、シンプルな内容です。
その上、レイヤー1・レイヤー2の概要やメリット、問題点についてきちんと理解しておくことによって、今後の仮想通貨の発展について詳しく学ぶことができます。
そこで今回は、レイヤー1、レイヤー2についてわかりやすい例えを交えながら、物事を一つ一つ理解できるようにご紹介します。
まだビットフライヤーの取引所を開設していない方はまずは仮想通貨取引所の登録手続きをおこないましょう
詳細はビットフライヤーの取引所開設をご覧ください
目次
レイヤー1(ベースレイヤー)とは?

レイヤー1とは、ベースレイヤーと呼ばれることもあります。
ベースレイヤーとは、名前からも分かるとおり、ベースとなるブロックチェーンプロトコルのことを指します。
簡単に言うとブロックチェーンそのものです。
そのため、性能の向上や低下はブロックチェーン上のプロダクトやサービスに大きく影響を与えます。
以下のようなものが、レイヤー1に該当します。
・BNB Smart Chain (BNB)
・Ethereum (ETH)
・Bitcoin(BTC)
・Solana
レイヤー1はすべてのベースとなるため、セキュリティが高く設定されています。
しかし、操作や変更はしにくくなります。
レイヤー1(ベースレイヤー)の仕組み

レイヤー1とは、仮想サーバーの上にデータやコンセンサス、アプリを搭載した集まりです。
つまり、仮想サーバー上のデータやコンセンサス、アプリは1つずつがブロックであり、それが連なるとブロックチェーンとなるのです。
ただ、仮想サーバー上に搭載しているのではなく、の一つのブロックの中に証明書と共に保管されています。
レイヤー1の現在の課題

レイヤー1は、登場した当初画期的なアイディアでした。
しかし、徐々に仮想通貨やブロックチェーンに注目が集まることによって、課題がでてきています。
それが「スケーラビリティ(拡張性)の欠如」です。
各ブロックの容量は限られていて処理に時間がかかる
各トランザクションは、ある程度の塊としてブロックに登録されます。
しかし、処理能力や1つのブロックに保存することができる容量は限られているので、取引量が多くなると処理することに時間がかかってしまうのです。
このことにより、スムーズに手続きが進まないという点が問題とされていました。
マイニングの手数料が高騰している
トランザクションが多くなった時には、マイナーは金銭的な条件のよいものを優先して処理するようになります。
つまり、より多くの方が利用することによって、マイニングの手数料が高くなってしまうのです。
手数料が高くなってしまうと、少額の決済には使わないという方が増えてしまいます。
そうすると、そのブロックチェーンを使う人が少なくなってしまうため、現在はこのスケーラビリティ問題を解決することが最優先の課題とされています。
ただ、これらの対策は大掛かりとなり、ビットコインとビットコインキャッシュのように意見が別れてハードフォークされる可能性もあります。
スケーラビリティ問題を解決するための方法と課題
スケーラビリティ問題が初めて登場したのは、2017年の仮想通貨バブルの時です。
その後、2020年頃からDeFiがブームになったことによって、再度深刻な問題として取り上げられるようになりました。
そんなスケーラビリティ問題を解決するための方法は、4つあります。
・取引のデータを小さくする
・ブロックを生成する時間を短くする
・ブロックチェーンの外で取引を行う
それぞれメリットもありますが、課題もあるのでチェックしていきましょう。
ブロックのサイズを大きくする
ブロックチェーンでは、1つのブロックに書き込めるデータの容量は限定されています。
そのため、単純にブロックのサイズを大きくして容量を増やせば、送金料を増やすことができるのです。
ビットコインは1MBですが、ビットコインキャッシュは8MBに増加している。
このように、ビットコインキャッシュはブロックを大きくして容量を増加してスケーラビリティ問題を解決しています。
しかし、ビットコインがあえてブロックサイズを変更しないのにも理由があります。
課題:マイニングが集中してしまう
ブロックサイズを大きくすることの問題は、マイナ-が集中してしまうことです。
ブロックサイズを大きくなると、マイニングにかかる負担が高くなってしまうことにより、マイニングを行える方が少なくなります。
そのことにより、ブロックチェーンの特徴である分散化があまり意味をなさなくなるのです。
ビットコイン・ビットコインキャッシュともに個人でマイニングを行うのは難しいので、ブロックチェーンである必要がないでしょう。
また、ビットコインの開発者であるサトシナカモト氏も「1MBがセキュリティ対策でもよい」と言われていることから、ブロックサイズを大きくすることは問題が多いと判断できます。
取引のデータを小さくする

取引のデータを小さくすることができれば、1つのブロックの中に保存することができる量が増えるため、スケーラビリティ問題の解決が可能となります。
このように、取引データを小さくすることをSegwitと呼びます。
レイヤー1の弱点を補うとされる対策の中でも有効性があるとされているのが、SegWitです。
SegWitはブロックデータの編成方法を変更することでビットコインの情報量が向上し、ブロックごとのトランザクション容量が増えました。
また、ソフトウォークで実装されたため更新されていないBitcoinノードでも、取引を処理することができます。
シャーディングは、トランザクションの情報量を向上させるために使用されます。
ネットワークとそのノードを異なるシャードに分割することで、作業負荷を分散し、トランザクション速度を向上させることができます。
実際にビットコインでは、すでにSeegwitに対応しており、スケーラビリティ問題の解決に挑んでいるようです。
SegWitが抱える課題
ただ、この方法だと1ブロックに記載するデータが増えるので、マイニングにかかるスペックが必要となります。
つまり、マイニングを行うことができる人が限られてしまい、中央集権的になってしまうことが問題とされています。
中央集権的になってしまうのであれば、ブロックチェーンを使用する意味がなくなってしまうため、異なる解決方法が必要とされています。
まだBybitの取引所を開設していない方はまずは仮想通貨取引所の登録手続きをおこないましょう
詳細はBybitの取引所開設をご覧ください
レイヤー2(セカンドレイヤー)とは?仕組みは?

レイヤー2とは、メインのブロックチェーン上にオフチェーンなどを用いて取引などを実行する技術になります。
もちろん、理論上レイヤー1で取引などをしても問題ありません。
わざわざオフチェーンなどを用いて取引などをするメリットとしては、高額なガス代、処理ができないなどのスケーラビリティ問題の解決ができます。
つまり、ブロックチェーン本体に負荷をかけず、高速な処理と低コストを実現できるのです。
簡単に言えばレイヤー1の改良版と言えるでしょう。
実際、ブロックチェーンのブロックは容量が決まっており、その容量めいいっぱいにデータを書き込むことになると処理が追いつかなかったり、送付遅延が起きたり、手数料が高くなったりしてしまいます。
そのため、取引の過程でいったんレイヤー1の外でブロック生成に必要となる計画処理を行って、最終的に結果のみをブロックチェーンに戻すという仕組みになっています。
このプロセスがあることによって、レイヤー1にかかる負担を減らして、できるだけ早く処理を行うことができるのです。
ちなみにこのスケーラビリティ問題が出てきたのは、暗号資産バブルが起きたときに取引を早く処理してもらうことが発端です。
最近では、オフチェーンでなくてもメインのブロックチェーンを応用したオンチェーンの開発も注目されています。
代表的な例としてPolygonやimmutableXというプロジェクトがあります。
クロスチェーンを実現も視野

実装していないものの、ビットコインとイーサリアムを仲介なしで直接交換することを可能にできます。
このことをクロスチェーンと言い、将来的には共通のスマートコントラクトで全てのチェーン上で動くプログラムが書けるようになることやチェーンの形を変えずにまとめることができるなど非常に期待が持てます。
まだコインチェックの取引所を開設していない方はまずは仮想通貨取引所の登録手続きをおこないましょう
詳細はコインチェックの取引所開設をご覧ください
代表的なレイヤー2の技術

スケーラビリティ問題を解決したレイヤー2ですが、レイヤー2の中でもさまざま種類があります。
・ライデンネットワーク
・Plasma
そこでここからは、代表的なレイヤー2の技術をご紹介します。
ライトニングネットワーク
取引量が多く、トランザクション処理に数時間かかるビットコインに使用され、最も人気なレイヤー2です。
ライトニングネットワークでは、双方向ペイメントチャネルという二者間でオフチェーン取引を行う仕組みを採用しています。
最終的な残高は後でメインチェーンに報告される仕組みになっており、全員のトランザクションが最終的に1つの記録にまとめられることでチャネルが繋がっていないもの同士でも高速で低コストな暗号資産の送付が可能となります。
ライデンネットワーク
ライトニングネットワークと同じようにスケーラビリティ問題を解決する技術かつ少額決済が可能です。
「ステート・チャネル」という仕組みを使い、ノード間で暗号資産をやりとりし、決済だけでなく「頻繁に状態が変わる取引」に効果が発揮されます。
また、プライバシーの強化も可能ですが、あらかじめデポジットされた額での送付を行うため、大量の送付には不向きでスマートコントラクトが実行できないなどのデメリットがあります。
それでも、独自トークンを発行してICOを行い、そのトークンはライデンネットワーク内で有料サービスを利用する際に手数料として使用できます。
Plasma
ブロックチェーン上で処理するオンチェーン型で、イーサリアムの共同創業者であるヴィタリック・ブテリン氏と、ライトニングネットワークを考案したジョセフ・プーン氏が考案しました。
仕組みとしては、親チェーンがイーサリアムブロックチェーンで、その下に子チェーンとしてPlasmaブロックチェーンを設け、その下にさらに子チェーンとして、Plasmaブロックチェーンの少額決済や分散型取引所、SNSの処理などを行わせるという形です。
オンチェーンのためスマートコントラクトが実装でき、ブロックチェーンに負荷をかけることなく高スピードかつ低コストを実現します。
まだビットポイントの取引所を開設していない方はまずは仮想通貨取引所の登録手続きをおこないましょう
詳細はビットポイントの取引所開設をご覧ください
レイヤー2の弱点

スケーラビリティ問題の解決ができたりとメリットが多いように思えますが、弱点もあります。
まず、オンチェーン型であればより時間がかからず高速で処理ができるものの、セキュリティに脆弱性があります。
2020年7月に一斉にチャネルを閉じることでトランザクションを捌ききれなくし、債務を回収できなくする攻撃が可能でトランザクションから資金を盗めるという論文が公開されました。
また、オンチェーン型は取引の一部を外部で行うため、すべての内容を把握することができず取引の透明性に問題があります。
まとめ

今後ますます仮想通貨の需要が増え、さまざまな仮想通貨も増え、問題点などが出てくると思います。
実際に何度も仮想通貨に関するブームが起き、市場規模も大きくなっています。
まだ、仮想通貨に関連する情報がネットや限られた書籍などの情報しかなく、情報を取得するのに株式投資などをする際と比べると容易ではありません。
どの情報が正しいのか取捨選択しながら、どのような仮想通貨に将来性があるのかを考えて仮想通貨と付き合わなければ被害にあってしまう可能性も高くなります。
レイヤー1やレイヤー2など細かで面倒であまり仮想通貨に関係しないと思ってしまうかもしれませんが、非常に重要な内容であり、レイヤー1やレイヤー2がわからなければ他の仮想通貨についてもわからないことが出てくることもありますのでしっかりと関連することも含めて投資する方など理解して覚えておく必要があるでしょう。
まだDMMビットコインの取引所を開設していない方はまずは仮想通貨取引所の登録手続きをおこないましょう